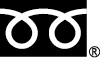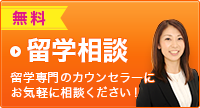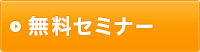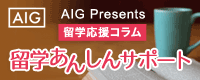大学生 奨学金完全ガイド

大学生の海外留学を検討する際、奨学金は費用面で非常に心強いサポーターです。本ガイドでは、大学生が留学費用を抑える方法から、返済不要の給付型奨学金や受給しやすい奨学金情報、短期留学向けの奨学金一覧、主要制度(JASSOやトビタテ!)の詳細、奨学金申請のコツ、学年別の準備スケジュール、奨学金と交換留学の併用術、よくある質問への回答、そして2025年現在の最新情報まで幅広く徹底解説します。経験豊富なカウンセラーがあなたの疑問解消もサポートしますので、ぜひ参考にしてみてください。
言語学留学について相談してみよう!
- 1. 大学生がお金をかけずに留学する方法
- 2. 【受給しやすい】大学生向け給付型奨学金厳選リスト
- 3. 【短期留学特化】返済不要の短期留学奨学金
- 4. 【主要制度】JASSO・トビタテ等の大型奨学金詳細
- 5. 【長期留学・海外進学】学位取得向け奨学金情報
- 6. 大学生の奨学金申請を成功させる実践テクニック
- 6-1. 採用されやすい奨学金の選び方
- 6-2. 志望理由書・エッセイの書き方のコツ
- 6-3. 推薦状の効果的な依頼方法
- 6-4. 面接・プレゼンテーションの成功法
- 6-5. 英語力不足でも申請できる奨学金
- 6-6. よくある失敗パターンと対策
- 6-7. 複数奨学金への戦略的申請
- 7. 【学年別】大学生の奨学金申請最適スケジュール
- 7-1. 大学1年生:基礎準備・情報収集の重要性
- 7-2. 大学2年生:本格的な申請準備・語学力向上
- 7-3. 大学3年生:就活との両立・最後のチャンス活用
- 7-4. 大学4年生:卒業後留学・大学院進学準備
- 7-5. 学年別の最適な奨学金選択
- 7-6. 早期準備のメリットと具体的アクション
- 8. 奨学金と交換留学の組み合わせ活用法
- 9. 大学生留学奨学金のよくある質問・疑問解決
- 10. 成功する留学の大学生奨学金取得サポート
1. 大学生がお金をかけずに留学する方法

大学生が留学費用を抑える方法として代表的なものに、次の3つがあります。
- 給付型奨学金の活用: 返済不要でもらえる奨学金を獲得して費用補助に充てる方法。授業料や生活費の一部/全額が支給され、自己負担を大幅に減らせます。例えば、日本学生支援機構(JASSO)の海外留学支援制度(協定派遣)奨学金では留学先に応じて月額8~12万円が給付され、さらに条件により渡航支援金(最大16万円)も支給されます。奨学金獲得には成績や計画の審査がありますが、採用されれば返済不要のため卒業後の負担もありません。
- 交換留学プログラムの利用: 在籍大学と海外大学の交換留学制度を利用し、授業料負担を軽減する方法です。交換留学では派遣先大学の授業料が免除または自大学の授業料のみで留学できるケースが多く、数十万円~数百万円の学費を節約できます。例えば自大学に通常支払う授業料(年間約50~100万円)のみで、留学先大学で半年~1年間学べるため大幅な費用削減になります。またJASSO奨学金などの給付型奨学金と併せて利用することで、生活費までカバーできる可能性があります。
- 格安留学の検討: 留学先やプログラムを工夫して費用そのものを下げる方法です。例えば学費・物価の安い国(アジアや東欧など)を選ぶ、夏休みなど休暇期間を利用した短期語学留学にする、ワーキングホリデーで渡航して現地収入を得ながら学ぶ、などの選択肢があります。フィリピンやマルタなどは授業料が比較的安くホームステイ費用も抑えられるため安い費用で語学研修が可能です。また最近は留学エージェントが提供する格安パッケージ(航空券・保険込みで○○万円など)もあるので活用を検討しましょう。
各方法のメリット・デメリット:
奨学金利用は審査準備の手間がありますが返済不要で恩恵大、交換留学は要件(語学力や成績)を満たせば学費面で有利ですが競争がある場合も、格安留学は行き先やプログラムの選択肢が限られる場合があります。ただし自分の目的や状況に合った方法を選べば、これらを組み合わせることも可能です。例えば「交換留学+奨学金」で学費も生活費もほぼ負担ゼロにしたケースや、「ワーホリ+語学学校短期コース」で働きながら低予算で留学するケースなど、さまざまな成功例があります。
費用削減効果の具体例:
仮にアメリカ大学に半年留学する場合、通常は授業料と生活費で約200万円かかるところ、交換留学制度を利用して授業料を自大学分の50万円に抑え、さらにJASSO奨学金月額10万円×6ヶ月=60万円と渡航支援金16万円を獲得できれば、自己負担は残り数十万円程度になります。結果的に半額以下の負担で留学が可能になります。このように各制度を駆使すれば、為替・物価・住居費の差を踏まえ自己負担を大幅に抑えられるケースがあります。
自分に最適な方法の選び方:
留学目的や経済状況によって適した方法は異なります。長期的に学位取得を目指すなら交換留学や奨学金フル活用を、短期で語学力アップが目的なら費用の安い国への短期留学を検討するなど、自分のプランに合った組み合わせを選びましょう。また情報収集も重要です。大学の国際課や留学エージェントに相談し、それぞれの制度の応募条件・期限を確認して計画的に準備を始めると安心です。
2. 【受給しやすい】大学生向け給付型奨学金厳選リスト
「給付型(返済不要)」の奨学金は魅力的ですが、その中でも対象が限定されて競争率が相対的に低い奨学金があります。競争率が低めだったり応募条件が限定的で狙い目の奨学金を厳選して紹介します。
受給しやすい奨学金の特徴・条件
一般に、有名な全国規模の奨学金よりも対象者が限定された奨学金の方が採用されやすい傾向があります。以下のような特徴に注目しましょう。
- 地方自治体の奨学金: 都道府県や市区町村が住民向けに提供する奨学金は、応募資格が「その地域出身・在住の学生」に限られるため競争率が低い場合があります。支給額は自治体によりますが、10万円~50万円程度の給付が多く、地元の国際交流推進の一環として実施されるケースが多いです。採用者には留学後に報告会参加や地域PRを求められることもありますが、地元枠ゆえに比較的狭き門ではないのがメリットです。例えば「○○県海外留学奨学金」「△△市留学支援制度」などが該当し、地元の教育委員会や国際交流協会のサイトで募集情報を探せます。
- 業界・分野特化型奨学金: ニッチな分野を対象とする奨学金も狙い目です。例えば「航空業界志望者向け」「エンジニア留学向け」「芸術専攻学生向け」など、特定業界や専攻に絞った奨学金は、その分野に該当する学生しか応募できません。競争相手が少なく採用率が高い傾向があり、自分の専攻や将来目指す業界に関連する制度がないか調べてみましょう。企業や業界団体、財団が提供するものにこうしたタイプが見られます。例えばIT人材向け奨学金、看護学生海外研修奨学金などが該当し、「自分の専門×奨学金」で検索してみると見つかることがあります。
- 地域限定・コミュニティ奨学金: 出身高校の同窓会奨学金や地元ロータリークラブの留学支援など、特定のコミュニティ限定の奨学金も要チェックです。応募者数が絞られるため採用されやすく、支給額も数十万円程度から中には100万円以上のものもあります。例えば地方銀行や信用金庫が地域貢献で設けている留学奨学金、地元の名士の寄付による基金(○○育英基金など)は、その地域出身者のみ対象なので見逃さず調査しましょう。
- 大学独自の奨学金制度: 在籍大学が自分の学生向けに設けている学内奨学金は、応募母集団が自大学生に限られるため合格のチャンスが高いです。例えば早稲田大学の「早稲田の栄光奨学金」(交換留学予定者に最大120万円給付)など、大学ごとに様々な制度があります。大学の国際交流センターや奨学金担当部署の情報を必ず確認し、学内選考に挑戦しましょう。学内奨学金は成績基準や家計基準を設けていることもありますが、「自校の学生を留学させるための奨学金」なので大学のサポートも厚く、採用後に大学名義の推薦が受けられるなどメリットもあります。
受給確率を上げる申請戦略
1人でも多くの採用枠を狙う:
受給しやすい奨学金とはいえ油断は禁物です。複数の奨学金に同時並行で応募し、当選確率を高めましょう。「奨学金は一つ受かれば充分」と思うかもしれませんが、もちろん複数採用も可能(併給不可の組み合わせを除く)です。仮に第一志望の奨学金に落ちても、他で受かれば結果オーライなので、リスク分散の意味でも積極的に複数応募がおすすめです。
応募条件にマッチするものを選ぶ:
自分のプロフィールと奨学金の趣旨が合致しているかを重視しましょう。たとえば地方自治体奨学金なら地元愛や将来の地域貢献の意思をアピール、分野特化奨学金ならその分野への熱意や実績を強調するなど、「選ばれやすい人材像」に自分を近づけて申請書を作成します。募集要項を熟読し、求められる人物像・条件に合致する奨学金を選ぶことで採用率が上がります。
締切と提出物の徹底管理:
競争率が低いとはいえ基本的な書類不備や締切遅れは致命的です。必要書類(成績証明書、推薦状、志望理由書など)を漏れなく準備し、余裕をもって提出しましょう。特に推薦状は依頼から取得まで時間がかかるので早めの行動が肝心です。
複数申請による成功率向上法:
繰り返しになりますが、「ダメもと」で良いので応募できるものには積極的に応募する姿勢が大切です。仮に奨学金AとBで併給が不可でも、両方に応募して両方受かった場合により条件の良い方を選択すればOKです(不採用だった場合の保険にもなります)。応募の際は他への応募状況を申告する欄がある場合もありますが、正直に書けば問題ありません。最終的にどれを受けるかは採用後に決めれば良いので、まずは門戸を広く叩くことが大事です。
3. 【短期留学特化】返済不要の短期留学奨学金
「1週間~3ヶ月程度の短期留学」を計画している大学生向けに、返済不要でもらえる短期留学奨学金をまとめます。夏休み・春休み期間を利用したプログラムや語学留学に特化した奨学金もありますので、有効活用してお金をかけずに短期留学を実現しましょう。
短期留学対応の奨学金一覧
短期留学向け奨学金には、以下のようなものがあります。
- 大学の短期研修プログラム奨学金: 大学が夏休みや春休みに実施する短期海外研修(語学研修や海外インターンシップ)向けに、参加学生へ給付される奨学金です。期間は1週間~3ヶ月程度で、採用者には5万~20万円程度が支給されるケースが多いです。日本の大学が派遣する公式プログラムのため比較的安心して応募でき、語学力要件が緩やかなこともあります。「〇〇大学海外研修奨学金」「短期語学留学奨励金」などが該当します。自分の大学にこうした制度があるか国際センターに確認してみましょう。
- 民間団体の短期留学奨学金: 国際交流団体や財団法人が提供する短期留学助成も存在します。例えば学独自助成(例:短期一律5万円等)や自治体助成などが「夏休み短期留学奨学金」などの名目で公募している場合があります。応募対象は大学生全般から地域限定まで様々ですが、支給額は数万円~十数万円程度が多めです。短期とはいえ返済不要なので、渡航費や滞在費の足しになります。
- 企業の語学留学支援奨学金: 語学習得を目的とした短期留学を支援するため、企業がCSRの一環で奨学金を出しているケースもあります。例えば英語教育サービス企業や旅行会社が主催する「短期語学留学奨学金コンテスト」等で、エッセイや動画審査に通ると奨学金がもらえるといったものです。支給額はプログラム費用相当(数十万円)だったり、航空券代として○○円支給など様々です。公募情報は各企業や関連サイトで発表されるので、定期的にチェックしてみましょう。
夏休み・春休み留学向け奨学金
長期の休暇を利用したサマープログラム/スプリングプログラム向けの奨学金は特に人気があります。多くの奨学金は応募時期が夏休み用は4~5月頃締切、春休み用は10~11月頃締切となる傾向があるため、早めの情報収集が鍵です。以下に代表例を挙げます。
- 「トビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラム(短期コース)」:以前は高校生向けもありましたが、大学生向け新プログラムでは自由度の高い計画で応募でき、1~3ヶ月の短期留学も対象となり得ます(※主に長期ですが内容次第で短期も可)。採用者には月額奨学金と準備金が支給されます。
- 「地方自治体の短期留学支援事業」:例)○○県海外短期研修奨学金...夏休み期間の語学研修参加者に10万円支給、など。自治体が高校生向けに行う例が多いですが、大学生対象のものも一部あります。地元自治体の国際課HP等で要チェック。
- 「財団主催の短期留学助成」:例)夏期留学奨学金(大学生対象、語学研修参加者に一律15万円給付)など。その年限りの募集も多いため、「短期留学 奨学金 大学生 2025」等で毎年検索して最新情報を得ましょう。
語学留学特化の奨学金制度
語学学校への短期留学費用をサポートする奨学金も存在します。例えば:
- 自治体の姉妹都市交流奨学金:自治体によっては姉妹都市への短期派遣プログラムを行い、語学研修費用を助成する例があります(例:「△△市姉妹都市短期留学奨励金」)。
- 大学語学センター奨学金:自大学の語学留学プログラム参加者に支給される奨学金です。応募者全員に一律支給してくれる太っ腹な大学もあります(例:ある大学では全参加者に一律5万円補助)。
短期留学奨学金の申請のコツ
短期でも目的意識を明確に:
短期留学は期間が短い分、「なぜこの短期間で何を得たいのか」を明確にすることが重要です。奨学金の応募書類でも「限られた期間で達成したい目標」や「具体的な学
習計画」をしっかり書きましょう。選考者に「短期でも意味のある留学だ」と納得してもらうことが大切です。
募集時期を逃さない:
前述の通り、夏休みプログラム向け奨学金は春先、春休み向けは秋に締切が集中します。学事暦を考えるとテストやレポートと重なる時期でもあるため、スケジュール管理が必要です。早めに応募要項を取り寄せ、提出物(成績証明書や語学スコア等)を揃えておきましょう。
語学力要件の確認:
語学留学奨学金でも最低限の語学力証明を求められる場合があります。短期留学の場合、それほど高いレベルは要求されないことも多いですが(英検2級程度など)、早めに条件を満たしておくと安心です。語学試験のスコア有効期限にも注意しましょう。
短期でも効果的な留学プランの立て方
短期留学を有意義にするため、事前準備と目標設定が鍵となります。例えば「TOEIC○点アップ」や「専門分野の現地調査」など具体的な目標を掲げてから渡航すると、限られた期間でも得るものが大きくなります。その過程や成果を書類に盛り込めれば、奨学金選考でも好印象を与えます。
また帰国後の活かし方も視野に入れましょう。「短期留学で磨いた語学力を○○に活かす」「現地で得た知見を卒論に反映させる」など将来につながるプランが描けていると、支援する側も応援しやすくなります。
成功する留学の短期留学プログラムも多数あります。費用を抑えたプランの提案や奨学金情報の提供も可能ですので、興味のある方はぜひご相談ください。
4. 【主要制度】JASSO・トビタテ等の大型奨学金詳細
ここでは、日本の大学生が利用できる代表的な大型奨学金制度である「JASSO海外留学支援制度」と「トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム」の詳細を解説します。それぞれ支給額や応募方法が異なるため、特徴を把握して上手に活用しましょう。
JASSO海外留学支援制度(協定派遣・短期派遣)
JASSO(日本学生支援機構)が実施する海外留学支援制度は、大学間協定に基づく交換留学や短期留学に参加する日本人学生に給付される奨学金です。特徴は以下の通りです。
- 支給額・採用人数:JASSO「海外留学支援制度(協定派遣)」の月額は、留学先地域により 86,000円/97,000円/106,000円/118,000円 の区分です。家計基準等を満たす場合の渡航支援は、プログラム種別により 10万円・16万円・20万円 のいずれかが一時金で支給されます。制度上、トビタテ(官民協働海外留学支援制度)との併給は不可。他の給付型との併給は、JASSO側の上限・規定内で可能な場合があります(詳細は募集要項をご確認ください)。支援予定人数は年度により異なりますが、2025年度の海外留学支援制度全体(協定派遣を含む)の支援予定人数は 16,529人 と公表されています。
- 応募方法: 個人で直接JASSOに応募するのではなく、大学を通じて申請します。在籍大学の国際交流担当部署が交換留学プログラム参加予定者の中から希望者を募り、成績や家計状況などの要件を満たす学生を推薦します。各大学に割り当て枠があり、書類審査を経てJASSOが採用者を決定します。応募時期は大学ごとに異なりますが、秋頃(留学前年)に募集・推薦を行うケースが多いです。詳しくは在籍大学の留学課に問い合わせましょう。
- 条件・選考基準: 応募には日本国籍または永住権が必要で、派遣プログラム終了後に帰国して学業を継続すること(卒業見込みも可)などの条件があります。学業成績が優秀で人物的にも優れていることが求められますが、具体的なGPA基準は明示されていません(大学側の選考基準によります)。経済的理由で自費留学が困難という条件もありますが、厳密な所得制限はなく比較的幅広い学生が対象です。採用後は留学報告書の提出などがありますが、返済義務はありません。なお他の給付型奨学金との併給は、相手側の奨学金が認めれば可能ですが、トビタテとの併給は不可など制限があります。
- ポイント: JASSO奨学金は大学交換留学の王道サポートです。採用されれば月々の生活費がかなり助かるため、交換留学を目指すなら是非とも狙いたい制度です。提出書類(申請書、推薦状、成績証明等)は大学経由ですが、自分でも志望理由書的な記載欄があれば丁寧に書き、担当者とコミュニケーションをとって抜け漏れなく手続きを進めましょう。
トビタテ!留学JAPAN 新・日本代表プログラム
「トビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラム」は、文部科学省とJASSOが主導し、民間企業等の寄付により運営されている官民協働の奨学金プログラムです。将来グローバルに活躍する日本人学生を育成することを目的とし、2014年から始まった「日本代表プログラム」が2023年度より新シリーズに移行しています。
- 支給内容: トビタテ新・日本代表プログラム(大学生等)の給付は、月額6万円/12万円/16万円 のいずれか(地域区分等による)に加え、留学準備金(渡航費等)、条件により授業料の支援もあります。2025年度(第17期)の大学生等対象の支援予定人数は計250人(イノベーター50人、STEAM100人、ダイバーシティ100人)。本制度は意欲・計画重視で、GPAや語学スコアの一律基準は設けていません(ただし留学実施に必要な語学力は各自で確保)。なお、JASSO協定派遣との併給は不可です。
- 対象・条件: 大学生(高専・専門学校生含む)および大学院生が対象です。在学中であれば学年は問わず応募できます(休学しての留学も可)。特徴的なのは成績や語学力よりも意欲重視の選考という点です。「成績・語学力不問!」と公式にうたっており、応募要件として特定のGPAやスコアは設けられていません(ただし採用後の留学実施までに必要な語学力は各自で確保する必要があります)。それよりも「将来グローバルリーダーとして社会に貢献したい高い志を持つ人」、「独自の留学計画を自ら設計できる人」を求めています。
- 応募方法・スケジュール: 所属大学を通じて応募する点はJASSOと同様ですが、トビタテの場合は大学ごとに学内選考会(書類・プレゼン等)が行われます。各大学から推薦枠内の学生がトビタテ事務局に提出され、最終選考(書類+面接)で採否が決定します。募集要項は毎年秋頃に公開、学内締切が11~12月、最終結果は翌年3月発表というタイムラインが一般的です。応募にはオンラインでのエントリーや留学計画書の提出が必要で、志望動機・計画の独創性が鍵となります。
- 選考のポイント: 「なぜその留学でなければならないか」が問われます。自分独自の課題設定と解決へのアプローチ、社会へのインパクトを強くアピールしましょう。型にはまった留学(例えば単に語学留学したいだけ)ではなく、自分ならではの挑戦(例:◯◯を研究し世界を変えたい→そのために△国の大学で学ぶ計画)を描くことが大切です。またプレゼンや面接も重視されるので、人に熱意を伝える練習も必要です。
- 採用後の義務等: 採用者は「日本代表」として、派遣前後の研修参加、帰国後の報告、同窓会コミュニティへの参加などが求められます。奨学金自体は返済不要ですが、得た経験を広く社会に還元することが期待されています。言い換えれば、それだけのバックアップを受ける価値のある人材として選ばれるわけです。
まとめると、JASSO奨学金は交換留学する学生の経済支援として最もベーシックな制度、トビタテ奨学金は独自の留学に挑戦する学生へのチャレンジ支援といった位置付けです。両方とも併願は可能ですが、同時採用は不可(トビタテ採用時はJASSO辞退)となります。自分の留学タイプに合わせて、どちらに力を入れるか戦略を立てると良いでしょう。
5. 【長期留学・海外進学】学位取得向け奨学金情報
大学を卒業した後、海外の大学や大学院に正規留学(学位取得)する場合の奨学金について解説します。長期留学は期間が長く費用も高額になりがちですが、その分各国政府や大学、国際機関などが提供する学位取得者向け奨学金が充実しています。ここでは代表的な奨学金制度と費用削減のコツをご紹介します。
海外大学・大学院進学の費用削減方法
海外で学位を取得する場合、授業料と生活費が何年間にもわたって必要になります。費用を抑える方法として次のようなものがあります。
- 現地の奨学金を狙う: 留学先国や大学が提供する奨学金に応募する方法です。多くの国が優秀な留学生を呼び込むために奨学金制度を持っています。例えばイギリス政府の「Chevening奨学金」(修士留学向け)、フランス政府の「エッフェル奨学金」、アメリカの大学のメリット奨学金などがあります。日本人であっても応募できるものが多く、授業料免除や月額給付が受けられます。ただし競争率は高めなので早めの準備が必要です。
- 日本の政府系奨学金(学位取得型): 文部科学省/JASSOは、海外の大学で学士・修士・博士課程を履修する人向けの奨学金も用意しています。「海外留学支援制度(学部学位取得型)」および「(大学院学位取得型)」がそれで、大学を直接海外に進学する高校卒業生や、大学卒業後に海外大学院へ進む人を支援します。例えば学部学位取得型では月額13.9万~35.2万円(地域により異なる)もの奨学金が最大4年間支給され、さらに渡航支援金1万円が支給されます。家庭の所得制限は2000万円以下と比較的緩やかで、2025年度は118名が採用されています。大学院学位取得型も修士2年・博士3年を上限に手厚い給付があります。これらは高校在学中~大学在学中に応募し、選抜試験(書類・面接)を経て採用が決まります。
- 各国政府のプログラム: 国別に見れば、中国政府奨学金、韓国政府奨学金、台湾の交換協会奨学金などアジア諸国も豊富です。欧米諸国も自国やEUの基金で留学生向け支援があります。例えばEUのエラスムス・ムンドゥス(複数学位取得プログラムに奨学金付きで参加可能)、ドイツのDAAD奨学金(ドイツ留学希望者に給付)など、多岐にわたります。行きたい国が決まっている場合、その国名+「奨学金 留学生」で検索すると情報が見つかりやすいです。
- 大学独自の奨学金・学費減免: 海外の大学自体が優秀な留学生に授業料免除やスカラーシップを提供する場合もあります。特に大学ランキング上位校や私立大学は豊富な奨学金枠を持っており、成績優秀者には学費全額免除+生活補助といったオファーが出ることもあります。学部留学では成績と課外活動実績、大学院では研究計画と推薦状が鍵です。合格後に自動的に奨学金選考対象となる場合も多いので、出願段階から奨学金獲得を視野に入れておきましょう。
学位取得型奨学金の概要
上記のように選択肢は多いですが、日本人学生に特に利用が多い奨学金をいくつか挙げます。
- 日本政府派遣留学生制度(旧国費留学生): 文部科学省が他国政府と協定して学生を派遣する制度。例えば日中、高校卒業後に中国の大学へ留学する「国費留学生」として授業料や生活費を負担する仕組みがあります。同様に日韓共同理工系留学生プロジェクトなどもあります。対象や募集時期が限られますが、公費派遣なので待遇は非常に良いです。
- 民間財団の海外留学奨学金: 伊藤忠、松下、笹川、平和中島などの財団が、大学院留学者向けに給付奨学金を出しています。多くは年間200~300万円を2年間給付など高額ですが、応募者も優秀層が集まるため準備が必要です。英語試験スコア、GREなどの成績も求められることがあります。
- 国際機関の奨学金プログラム: 国連や世界銀行が関与する奨学金もあります。例えば世界銀行の「ジョイントジャパン奨学金」は開発途上国の方対象なので日本人は対象外ですが、逆にJICAが実施する「長期研修」枠(途上国の人を日本に呼ぶ)とは別に、日本人が海外大学院で開発学を学ぶプログラムなど探すと出てくる場合があります。
国別の政府奨学金制度
アメリカ:日本人が使える代表的なものにフルブライト奨学金があります。大学院留学者に対し授業料と生活費を支給(返済不要)する伝統ある制度です。年間数名と狭き門ですが、アメリカで修士・博士を目指すなら挑戦する価値があります。
イギリス:前述のChevening(チーブニング)は英国政府が世界中から留学生を募る奨学金で、日本人枠もあります。1年間の修士課程向けで授業料全額+生活費支給という内容です。その他各大学も奨学金を独自に持っているので、志望大学のScholarshipsページを確認しましょう。
オーストラリア・ニュージーランド:オーストラリア政府のエンデバー奨学金は2020年に終了しましたが、各大学ごとの奨学金は豊富です。ニュージーランドは大学ごとにInternational Student Scholarshipがあり、授業料一部免除が一般的です。
その他ヨーロッパ:ドイツのDAAD、日本人向けは大学院留学や博士研究に給付金。フランスはエッフェル以外にも地方自治体奨学金があります。
アジア:中国政府奨学金は日本人も応募可能で、授業料免除+寮費無料+月額数千元の支給など手厚いです。韓国も韓国政府奨学金で授業料+生活費支給があります。シンガポールや香港の大学は成績優秀な留学生に全額奨学金を提供する制度があり、高い競争率ですがチャンスがあります。
海外大学進学奨学金の詳細はこちら:
海外大学進学奨学金ガイド(成功する留学)
※上記リンク先で各国・各奨学金の最新情報や応募要件をまとめていますので、長期留学を目指す方はぜひ参考にしてください。
短期留学から海外進学への段階的アプローチ
「いきなり海外の大学に進むのはハードルが高い...」という場合、短期留学→交換留学→海外進学とステップを踏む方法もあります。大学在学中に短期や交換で海外経験を積み、人脈や語学力、自信をつけた上で卒業後に本格的な海外進学に挑戦するパターンです。短期留学や交換留学で奨学金をもらっておけば経済的負担も抑えられますし、留学経験が志望動機として海外大学の出願で評価されることもあります。
実際に、「学部交換留学(JASSO奨学金利用)→ 帰国後就活ではなく海外大学院進学(奨学金獲得)」という道を選ぶ学生も増えています。成功する留学では、そのような段階的プランの相談にも応じていますので、「将来は海外大学に進みたいが不安がある」という方もまずは短期プログラムなどからチャレンジしてみましょう。
6. 大学生の奨学金申請を成功させる実践テクニック
奨学金に合格(採用)するためには、単に募集要項を満たすだけでなく他の応募者より魅力的にアピールする工夫が必要です。ここでは奨学金申請の実践的なコツを紹介します。志望理由書の書き方から推薦状依頼のポイント、面接対策まで網羅しており、採用率アップに役立ててください。
採用されやすい奨学金の選び方
前述のとおり、まずは適切な奨学金選びがスタートです。自分が応募資格を満たし、かつ自分の強みを活かせる奨学金を選ぶと合格率が上がります。
- 倍率情報をチェック: 公募人数や過去の採用実績が公開されている場合、それを手がかりにしましょう。採用人数÷応募人数で大まかな倍率が見えることがあります。例えば採用10名で応募100名なら倍率10倍程度です。倍率が高すぎるものばかり狙うより、適度な競争率のものも混ぜて応募する方が安全策です。
- 応募要件とのマッチ度: 自分の成績や語学力、専攻分野、留学計画が募集側のニーズに合っているかを見極めます。例えば「環境分野で社会貢献意欲のある学生対象」という奨学金なら、環境学専攻で関連プロジェクト経験がある学生は有利です。このように「これは自分にピッタリだ!」と思える奨学金には力を入れるべきです。
- 奨学金ごとの特色を理解: 選考委員会の視点を意識します。財団系なら創設者の理念(人間力重視など)に沿った人材を選ぶ傾向があったり、大学内奨学金なら学業成績を重視するなど、傾向があります。過去の採用者の声や応募要項の文言から何を重視しているか推測し、自分のアピールポイントを調整しましょう。
志望理由書・エッセイの書き方のコツ
志望理由書(エッセイ)は最重要書類の一つです。書き方のポイントは以下です。
- 構成を練る: だらだら書くのは厳禁です。一般的には「序論(志望動機の概要)→本論(具体的な計画・将来展望)→結論(熱意の再アピール)」の構成が読みやすいです。文字数制限内で伝えたい要素を箇条書きし、推敲を重ねましょう。
- 差別化ポイントを盛り込む: 他の応募者と差をつけるため、自分だけのエピソードや視点を入れます。留学を志すきっかけとなった体験、課題意識、それに基づく具体的な留学計画など、「あなたにしか書けない内容」があると選考委員の心に残ります。
- 奨学金の目的に絡める: 奨学金ごとに目的(例:「国際的人材育成」「〇〇分野の振興」等)があるので、自分の留学目的がそれと合致していることを示します。「本奨学金の支援を得て〇〇という目標を達成し、将来△△として社会に還元したい」といった熱意とビジョンを明確に伝えましょう。
- 読みやすい文章に: 尊敬語や謙譲語を乱用せず、明瞭かつシンプルな日本語/英語で書きます。専門用語は説明を加え、固有名詞や数字も正確に。何度も読み返し、友人や先生にもチェックをお願いして誤字脱字や論理の飛躍がないか確認しましょう。
推薦状の効果的な依頼方法
推薦状(推薦書)は信頼性を高める重要書類です。教授や上司などに依頼する際のポイントを押さえましょう。
- 早めに依頼: 推薦者には最低でも締切の1ヶ月前、可能なら2ヶ月前にはお願いしましょう。直前では十分な内容を書いてもらえなかったり辞退されるリスクがあります。「◯月◯日締切で、このような留学を計画しています。ぜひ推薦書をご執筆いただけないでしょうか?」と丁寧にお願いし、必要書式や宛先、提出方法も伝えます。
- 情報提供をする: 推薦者が書きやすいよう、自分の志望理由書ドラフトや履歴書、アピールしたい点のメモをお渡ししましょう。推薦者自身があなたをよく知っていても、具体的な留学計画までは知らない場合があります。「推薦書に盛り込んでほしいポイント」としてお願いするのもありです(例:「英語での授業についていける学力があることを触れていただけると助かります」等)。
- 礼儀を忘れずに: 推薦していただくことへの感謝の気持ちを伝えましょう。書き上がった後もお礼を述べ、もし合否が出たら結果報告とお礼を改めて伝えると良いです。このような誠実な対応は、今後また依頼するときにも快く引き受けてもらえる鍵です。
面接・プレゼンテーションの成功法
大型奨学金では面接試験や場合によってはプレゼン(口頭発表)が課されることがあります。対策のコツは以下です。
- 想定問答を準備: 志望理由、留学計画の詳細、将来の目標、奨学金をどう活かすか、なぜその国・大学か、自分の強み・弱み...など聞かれそうな質問をリストアップし、自分なりの回答を用意しましょう。日本語面接でもしどろもどろになると印象が下がるので、家族や友人に面接官役をしてもらい練習すると効果的です。
- 英語/現地語での質疑応答: 面接が英語で行われる場合(トビタテの一部や海外大学の奨学金など)もあります。その場合は留学動機や専門内容を英語で説明する練習が必要です。専門用語の英訳や、自分の経歴紹介をスムーズに言えるように準備しておきます。
- プレゼン資料のポイント: もし事前にプレゼン資料提出や当日スライド発表があるなら、図表や写真を活用し視覚的に訴えると効果的です。ただしシンプル&明快が鉄則で、指定時間内に収まるよう何度もリハーサルしましょう。聞き手(選考委員)は専門外の方もいるかもしれないので、専門用語はかみ砕きながら話します。
- 態度と熱意: 面接では内容だけでなく人柄や熱意も見られます。ハキハキと挨拶・応答し、わからないことは素直に「~について現在勉強中です」など正直に答えましょう。笑顔とアイコンタクトも忘れずに。自信なさげより、少しくらい緊張しても熱い想いを伝える方が印象に残ります。
英語力不足でも申請できる奨学金
「留学したいけど英語(語学)に自信がない...」という学生もいるでしょう。実は奨学金の中には語学力条件を問わないものもあります。例えばトビタテの大学生コースは応募時点で語学スコア不問です。また地方自治体奨学金なども英語力証明を求めない場合があります。ただし留学する以上、最低限の語学力は必要になるので、応募までにできる限りのスコア向上を図りましょう。
語学要件がある奨学金でも、応募時点で間に合わなければ「◯◯のスコアは現在△△だが、渡航までに目標の□□に達するよう努力している」など努力中であることを伝えると良いです。語学は直前まで伸ばせる要素なので、弱みを見せつつ向上心を示せればマイナスばかりではありません。
よくある失敗パターンと対策
- 書類の不備・遅延: 必要書類の欠落や提出ミスで失格になるケースが散見されます。提出前に必ず第三者(先生や友人)にチェックしてもらいましょう。特に封入漏れ、押印漏れ、期限間違いなどは致命的です。
- 志望理由が抽象的: 「異文化を学びたい」「視野を広げたい」だけでは弱いです。他の人も言うような抽象論ではなく、具体的な目的や計画を書くようにしましょう。
- 消極的な印象を与える: 面接やエッセイで受け身な姿勢はNGです。「機会があれば挑戦したいと思います」より「この奨学金を得て必ずや◯◯を実現します!」くらいの意気込みが伝わる方が評価されます。
- ルール無視: 例えば決められたフォーマットを使わない、字数を大幅に超える/不足するといった基本ルール違反はマイナスです。募集要項の指示は厳守し、その中で工夫するようにしましょう。
複数奨学金への戦略的申請
最後に、複数応募の戦略について補足します。既に述べたように併願はメリットが大きいですが、実際に複数採用となった場合のことも考えておきます。一般に、給付型奨学金同士の併給は不可の場合が多いです(特に双方から生活費をもらう場合など)。採用後にはどちらか一方を選択する必要が出てくるでしょう。その際は金額の大小だけでなく、付随する義務(報告会出席など)やネットワークなどソフト面も考慮して選びます。
また、貸与型奨学金や教育ローンは給付型と併用可能なことが多いです。給付型に落ちたときのため、貸与型(例:JASSO第二種奨学金)を併願し、給付型が受かったら貸与は辞退する、といった使い分けも考えられます。計画段階で「最悪全部落ちたらこの貸与型を利用しよう」というプランBまで立てておくと安心です。
7. 【学年別】大学生の奨学金申請最適スケジュール

奨学金申請はいつから準備すれば良いのでしょうか?大学1年生~4年生まで、学年ごとに最適なスケジュールと準備ポイントをまとめました。早い段階から動き出すことで、有利に奨学金を獲得できる可能性が高まります。「思い立ったが吉日」で、今の学年に応じた行動を起こしましょう。
大学1年生:基礎準備・情報収集の重要性
1年生のうちは留学自体まだ先...と思うかもしれませんが、情報収集は早ければ早いほど有利です。
- 奨学金の存在を知る: 世の中にどんな奨学金があるのか、まずは広くリサーチしましょう。大学の留学センター主催の説明会や、インターネットで「留学 奨学金 大学生」と検索して概要を掴みます。高額な給付型は年1回募集がほとんどなので、逃さないようにカレンダーに記しておきます。
- 語学力の土台作り: 1年次から英語など外国語の勉強に力を入れましょう。TOEFLやIELTSなど将来必要になりそうな試験について調べ、単語学習や基礎力強化を始めると後が楽です。英語以外の留学(例:スペイン語圏など)を考えるなら、その言語の勉強も早めに着手すると◎。
- 成績をしっかり取る: 1年次の成績は交換留学や奨学金選考で見られることがあります。特に語学系・専門基礎科目で高得点を取っておくと印象が良いです。授業にも手を抜かず、GPAをキープしておきましょう。
- 課外活動に参加: ボランティアや部活など課外活動も、奨学金応募時のエピソードになります。興味あることに挑戦して、「自分はこんな活動を頑張っています」と言える種をまいておきましょう。
大学2年生:本格的な申請準備・語学力向上
2年生になると、交換留学や奨学金応募の具体的準備が始まります。
- 交換留学の計画: 3年次に交換留学したい場合、2年の秋~冬には出願です。従って2年生の春~夏に募集要項が発表され、説明会などがあります。これに伴いJASSO奨学金の学内募集も行われるので、交換留学希望者は2年生の前半から情報を集めておきます。
- 語学スコア取得: 交換留学や奨学金応募でTOEFL/IELTSスコア提出が必要なら、2年のうちに目標スコアを取得しましょう。夏休みに語学留学や集中講座を受けるのも手です。語学試験は前倒しで準備し、遅くとも応募半年前までに必要点数をクリアできるよう計画します。
- 奨学金応募開始: トビタテやその他財団奨学金は早い人で2年終了時から応募可能なものもあります。例えば「トビタテ第◯期」は3年次派遣向けに2年秋募集、といったケースです。自分が応募できるタイミングかどうか確認し、チャンスがあれば挑戦します。
- 志望理由のブラッシュアップ: この頃から「自分は何のために留学したいのか」を言語化しておきましょう。将来像や関心分野もより明確になっているはずなので、1年時に漠然と思っていた動機を深掘りし、奨学金のエッセイに生かせるネタを整理します。
大学3年生:就活との両立・最後のチャンス活用
3年生は就職活動や研究室配属など忙しい時期ですが、奨学金応募の大詰めでもあります。
- 交換留学の実施・応募: 多くの学生は3年次に交換留学を実施します。この際JASSO奨学金に採用されている可能性が高いです。渡航前後の手続きや報告書提出など漏れなく行いましょう。また、まだ交換留学に行っていない人も、3年秋募集で4年次派遣(卒業延期)という形で最後のチャンスがある大学もあります。
- トビタテ等の応募: トビタテ日本代表プログラムは通常3年秋~冬に応募し、4年開始時に派遣となります(卒業を1年延ばすケースが多い)。したがって3年の冬が応募ラッシュです。他にも民間財団の奨学金(大学院留学向け等)に学部3年で応募するものもあります。就活準備と並行になりますが、計画的に両立しましょう。
- 就活or留学か方向性決定: 奨学金申請とは直接関係ありませんが、自分が4年生で卒業→就職か、卒業後留学(大学院等)か、このあたりで方向を決める必要があります。海外大学院進学を目指すなら、願書準備と並行して奨学金(例えば日本の財団系は学部最終学年で応募)に取り組みます。就職する場合でも「内定後に奨学金で短期留学」など企業留学制度を狙う選択肢もあります。
- 成績の維持: 3年前期までの成績が奨学金審査に使われることが多いです。ゼミや専門科目で忙しくなりますが、最後までGPA管理を怠らずに。特に「語学」「専門必修」での高成績は対外的な評価ポイントです。
大学4年生:卒業後留学・大学院進学準備
4年生では通常、新規に学部生対象の奨学金応募は少なくなります。ただ卒業後のプランに向けた準備を進めましょう。
- 大学院留学の奨学金応募: 例えばJASSOの大学院学位取得型奨学金は4年秋に募集があります。また財団系(伊藤忠や松下など)は毎年秋に募集開始、年末~年明け締切です。卒業研究と並行して大変ですが、社会人になる前のラストチャンスと思って頑張りましょう。
- 交換留学派遣中/直後なら報告と次の一手: 4年の春まで交換留学していた人は帰国報告書等をまとめます。その経験を活かし、大学院志望理由書や企業面接で語れるよう整理するのも大切です。
- 卒業論文と両立: 4年生は卒論執筆が最優先ですが、奨学金応募書類の締切も容赦なくやってきます。逆算スケジュールで計画を立て、10~11月頃締切の奨学金があるなら夏休み中にドラフトを書くなど前倒ししましょう。
- 社会人用奨学金の検討: 卒業後すぐ留学しない場合も、社会人経験を経て留学する際の奨学金(例:官庁派遣や会社の社費留学、または社会人向けトビタテ枠等)が将来使えます。今は就職を選ぶ人も、将来の留学機会と奨学金制度について情報収集だけは続けておくと良いでしょう。
学年別の最適な奨学金選択
各学年で出てくる奨学金を簡単にまとめると:
- 1年: 情報収集期。高額給付型(トビタテ等)の存在を知り、語学&成績の土台作り。
- 2年: 交換留学申し込み準備、語学スコア取得。場合によってトビタテ等に挑戦。
- 3年: 交換留学実施。トビタテ本番、財団奨学金応募。就活と進路決定。
- 4年: 大学院留学奨学金応募(秋)。卒業準備&将来計画。
もちろん人によって異なりますが、おおむねこの流れになります。「早期準備のメリット」は計り知れません。時間がある1~2年のうちにできるだけ先手を打っておけば、後から「◯◯しておけばよかった...」と悔やまずに済みます。
早期準備のメリットと具体的アクション
- 締切に追われない安心感: 余裕を持って準備すればミスも減り、結果として合格率アップにつながります。「留学したい」と思ったらすぐ動く、が吉です。
- 選択肢が広がる: 時間があればあるほど、応募できる奨学金の数も増えます。高1・高2から準備する高校生もいるくらいです。大学生であれば1年でも早く情報を集め始めることで、自分に合う奨学金を見逃さずに済みます。
- アクション例: 今すぐできることとして、興味のある奨学金の公式サイトをブックマーク、過去の応募書類フォーマットを入手してみる、英語の勉強を開始する、留学経験者に話を聞く、などがあります。一歩踏み出せば、あとは雪だるま式に情報も集まってくるでしょう。
8. 奨学金と交換留学の組み合わせ活用法
交換留学と奨学金を上手に組み合わせることで、留学費用を劇的に削減できます。ここではそのメリットと具体的な活用法、注意点を解説します。
奨学金+交換留学併用のメリット
- 学費・生活費の大幅節約: 交換留学では派遣先大学の授業料が免除され、自大学の授業料だけで留学できます。そこに給付型奨学金を併用すれば、渡航費や現地生活費までカバー可能です。例えば交換留学で100万円の学費免除を受け、さらにJASSO奨学金で月8万円×10ヶ月=80万円+渡航支援金16万円を受給できれば、計約196万円の支援となり、自己負担は渡航諸経費のごく一部だけ...というケースも実現します。
- 自己資金ゼロ留学も夢じゃない: 実際に「交換留学+奨学金併用」でほぼ自己負担ゼロで留学した学生もいます。大学が授業料を相殺し、奨学金で寮費・航空券代がまかなえれば、貯金がなくても留学できるのです。「お金がないから留学無理」とあきらめていた人も、この組み合わせを知れば道が開けるでしょう。
- 学業への専念: 経済的心配が減ることで、留学先でアルバイトに追われず学業に専念できます。成果を出しやすくなり、結果的に留学自体の充実度も高まります。
費用削減効果のシミュレーション
ケース例:
私立大学3年生のAさんが1年間アメリカの大学へ交換留学する場合。
- 通常かかる費用(自己手配留学の場合):米大授業料150万円+滞在費120万円+航空券等30万円=約300万円。
- 交換留学利用:自大学の授業料(年間100万円)のみ負担。授業料150万円節約。
- JASSO奨学金利用:月額指定都市12万円×12ヶ月=144万円+渡航支援金16万円=160万円給付。
- 結果: 300万円のところ、自己負担は自大学授業料100万円のみ。奨学金160万円が生活費等に充当され、むしろ+60万円プラス(不足分を賄い余りある)という計算に。極端な例ですが、これだけの効果があり得ます。
もちろん為替レートや生活水準で変わりますが、併用の威力が伝わるでしょう。奨学金が全額出なくても、ほとんどの費用をカバーできる可能性があります。
併用可能な奨学金制度
交換留学と併用できる主な奨学金としては:
- JASSO海外留学支援制度(協定派遣) -- 交換留学する学生向け奨学金の代表。基本的に交換留学=これをセットで申請するイメージです。
- 大学の交換留学奨学金 -- 大学独自に交換派遣生へ支給する奨学金。学内募集で数十万円支給など、併願OKな場合が多いです。
- 地方自治体/財団の給付奨学金 -- 交換留学でも応募可能なら、JASSOと二重受給できるか要確認ですが、団体側が禁止していなければ受け取れます。例:地元県の留学奨学金+JASSOの併用など。
- 企業の留学奨学金 -- 例えば〇〇財団など民間奨学金は交換留学でも対象となる場合があります。採用通知後、JASSOとの調整が必要なこともありますが、可能なケースもあります。
大切なのは各制度の併給規定を確認することです。JASSOは他の給付型奨学金との併給を原則認めていませんが、相手側がOKなら受給可能とされています。トビタテとは不可なので注意。地方自治体や大学奨学金はJASSOと併給OKの場合が多いです。
申請タイミングの調整方法
交換留学と奨学金、それぞれ応募時期があります。これを上手に噛み合わせる必要があります。
- 交換留学内定前でも奨学金応募: 例えば財団奨学金は「留学計画が具体的であること」が条件なので、交換留学出願中でも「◯大学に交換留学予定、結果待ち」として応募可能な場合があります。結果が出る前に奨学金締切が来ることも多いため、同時並行で手続きを進める度胸も必要です。
- 学内選考の日程確認: 大学の交換留学選考→JASSO推薦応募→採否通知という流れがあります。さらに並行してトビタテ応募や他奨学金応募があると、スケジュール管理が複雑になります。カレンダーに全て書き出して逆算しましょう。「○月△日:交換留学願書締切、○月×日:奨学金A締切、○月○日:奨学金B面接」等、見える化すると計画が立てやすいです。
- 優先順位の決定: 万一スケジュールが被りすぎる場合は、どれに注力すべきか決めます。例えば「どうしても行きたい大学への交換留学に全力投球し、奨学金応募は次点」という選択もありです。逆に交換留学先に強いこだわりがなければ奨学金優先で考えても良いでしょう。
9. 大学生留学奨学金のよくある質問・疑問解決
奨学金について大学生から寄せられるよくある質問をQ&A形式でまとめました。疑問や不安を事前に解消して、スムーズに奨学金応募・留学準備を進めましょう。
Q1: 複数の奨学金を同時に受け取ることはできますか?
A1: 場合によります。複数奨学金の併用(併給)は、各奨学金の規定次第です。給付型奨学金同士は併給不可が多いですが、一部例外もあります。例えば「トビタテ採用者は他の給付型を原則辞退」という決まりがあります。JASSOと地方自治体奨学金は併用可能な場合が多いですが、自治体側の規定により「他の給付奨学金と重複受給不可」とあるとNGです。応募要項の「併給ルール」を必ず確認してください。貸与型(日本学生支援機構第一種/第二種など)との併用は一般にOKです。複数応募し、複数採用となった場合は、最終的に最も条件の良いものを選ぶか、併用可能な組み合わせなら両方受け取る形になります。
Q2: 奨学金が不採用だった場合の対処法は?
A2: 残念ながら不採用だった場合も、まだ手はあります。まず別の奨学金に再挑戦しましょう。一度落ちても次回募集で採用されることも十分あり得ます。また、他の資金調達手段として教育ローンや大学の留学貸付制度を検討するのも一つです。日本政策金融公庫の「国の教育ローン」や民間銀行の留学ローンは低金利で借りられます。返済は必要ですが、将来の自己投資と割り切って利用する人もいます。さらに大学によっては「留学渡航支援貸付」など無利子貸与制度があるので確認してください。アルバイトで資金を貯める、クラウドファンディングで支援を募る例もあります。不採用でも夢を諦めず、別ルートでの資金計画を立て直しましょう。
Q3: 家計状況や成績に自信がない場合、奨学金は無理でしょうか?
A3: いいえ、あきらめる必要はありません。奨学金には経済条件や成績基準が緩いものもあります。例えば家計基準がある奨学金では、逆に低所得世帯を優先するケースも多いです(所得制限内なら応募OK)。成績についても、「平均3.5以上」など基準がある場合は努力して近づけるか、それを補う課外活動実績でアピールするなど方法があります。また語学力不問のトビタテのように、成績・家計より意欲重視の奨学金もあります。大切なのは自分に合った奨学金を探すことです。完璧な優等生でなくてもチャンスはあります。
Q4: 英語力が不足している場合、どう準備すればいいですか?
A4: 語学力向上策を早急に取りましょう。TOEFLやIELTSのスコアが要求される奨学金なら、まずは目標スコアを設定し勉強開始です。大学の語学センターや民間のオンライン英会話、単語アプリなど活用して、とにかく毎日継続してください。短期集中でスコアを上げたいなら語学留学や語学合宿に参加するのも有効です。応募期限に間に合わない場合は、応募書類で「現在○○点だが出発までに△△点取得予定」と記載し、選考委員に努力中であることを伝えます。また英語以外の留学(例:スペイン留学)でも、まず英語で最低限コミュニケーション取れるようにしておくと安心です。語学力は伸びしろが見られれば加点要素になります。「向上心」があるかどうかも含めて評価されると捉え、前向きに取り組みましょう。
Q5: 奨学金申請書類の準備で困った時はどうすればいい?
A5: 自分一人で抱え込まず、周囲に相談しましょう。大学の留学アドバイザーや教務担当、指導教員は頼れる存在です。志望理由書の下書きを見てもらったり、必要書類(在籍証明・成績証明など)の発行依頼方法を教えてもらえます。また、留学エージェントやOB/OGに相談するのも一手です。成功する留学のようなエージェントでは奨学金申請サポートも行っていますし、過去に同じ奨学金を取った先輩がいれば体験談を聞けます。行き詰まったら一人で悩まず、とにかく誰かに話してみてください。新しい解決策が見えてくることが多いです。
Q6: 奨学金以外で留学費用を調達する方法はありますか?
A6: はい、奨学金以外にもいくつか方法があります。教育ローン/学生ローンは、公的・民間の留学ローンを借りる方法で、返済義務はありますが、どうしても奨学金が得られない場合の最終手段です。クラウドファンディングは、最近増えている方法で、自分の留学計画をSNS等で広報し、賛同者から資金を募ります。ただし返礼や目標達成責任が伴うため、簡単ではありませんが独自の夢がある人は挑戦してみる価値があります。社内制度の活用(社会人の場合)では、卒業後すぐではなく一旦就職するなら、勤務先の社費留学制度や休職留学制度を利用する道もあります。自己資金の貯蓄も地道ですが大切で、バイトやインターンでコツコツ貯めれば、目標額を決めて計画的に貯金すれば、奨学金がなくても渡航できるぐらい貯まるかもしれません(特に物価の安い国なら100万円貯めれば十分な場合も)。
Q7: 留学から帰国後に報告義務などありますか?
A7: 奨学金によります。報告義務としては、JASSOやトビタテでは帰国後の報告書提出やアンケート回答が求められます。トビタテの場合は事後研修や成果発表会などにも参加します。地方自治体奨学金だと帰国後に知事や市長への表敬訪問やレポート提出、報告会登壇といったケースもあります。民間財団でも、帰国後に体験記提出やOB会参加をお願いされることがあります。ただ、いずれも難しいことではなく、自分の留学体験を共有する程度です。義務違反をすると返還請求など厳しい罰則が課される奨学金(例えば途中で留学をやめたら返金)はごく一部なので、普通に終了すれば問題ありません。むしろ報告会等はネットワーク作りの場にもなるので、積極的に参加すると良いでしょう。
以上、よくある質問にお答えしました。他にも疑問があれば、「成功する留学」の無料相談等でお気軽にお問い合わせください。
10. 成功する留学の大学生奨学金取得サポート
30年以上の実績を持つアジアNo.1留学エージェント「成功する留学」では、大学生の奨学金取得から留学実現までを一貫サポートしています。累計25万人以上の留学を支援してきた経験から、奨学金に関する豊富なノウハウとネットワークを活かし、あなたの「お金をかけずに留学したい」という夢を全力でお手伝いします。
奨学金申請から留学実現までの一貫サポート
当社では、留学カウンセリングの段階から奨学金を見据えたプランニングを行います。「どの奨学金にいつ応募すべきか」「留学先の選択肢と奨学金の組み合わせ」など、最適解をご提案。奨学金に応募する際は書類作成のアドバイスから面接練習まで、合格に向けた具体的サポートを提供します。奨学金が取れた後も、留学先への出願手続き、ビザ取得、渡航準備、留学中のフォロー、帰国後のキャリア相談までトータルで伴走します。
志望理由書・エッセイ作成支援
プロのカウンセラーが、あなたの志望理由書やエッセイ作成をサポートします。「どんなエピソードを盛り込めば魅力的か」「文章構成はこれで伝わるか」など、第三者視点でアドバイス。もちろんオリジナリティを尊重しつつ、選考委員に刺さるポイントを押さえた添削を行います。初めてエッセイを書く方も安心してください。一緒にあなたの熱意を形にしましょう。
面接対策・プレゼンテーション指導
奨学金の最終面接に向けては、模擬面接で徹底トレーニングします。想定質問の洗い出しから回答のフィードバック、話し方のコツまで細かく指導。必要に応じて英語面接の練習も実施します。またトビタテ等でプレゼンが必要な場合、資料作成やスピーチの練習もお任せください。場数を踏んだカウンセラーが、本番で実力を最大限発揮できるようサポートします。
英語力向上サポート・学習プラン
奨学金応募や留学に不可欠な語学力アップも、当社提携の語学研修プログラムやオンラインレッスンでバックアップします。出発前に無料で受講できる英会話レッスンもご用意しています(サポートお申込みの方対象)。「TOEFLスコアを〇点上げたい」「面接までにスピーキングを鍛えたい」等、一人ひとりの目標に合わせて学習プランを提案します。語学のプロ講師による効率的な指導で、短期間でも成果を出しましょう。
最適な奨学金選択のアドバイス
奨学金は本記事で紹介したように多種多様です。自分だけでは選びきれない...という方も、当社カウンセラーがヒアリングの上であなたに合った奨学金をピックアップします。「成績は平均◯くらいだけど取れるものある?」「地方出身なので県の奨学金狙いたい」など、何でもご相談ください。カウンセラー自身も奨学金留学経験者が多く、リアルな体験に基づくアドバイスが可能です。
交換留学プログラムとの組み合わせ提案
成功する留学は世界各国の大学・語学学校と提携しており、交換留学プログラムや手頃な留学プランも豊富に扱っています。奨学金と組み合わせることで最強のコストパフォーマンスを実現できるプランを一緒に考えます。「奨学金をもらって、この提携校に半年留学」「ワーキングホリデーで働きつつ、この奨学金で短期語学研修」といった柔軟な提案ができるのも当社の強みです。
無料相談・個別カウンセリングのご案内
成功する留学の無料個別カウンセリングでは、奨学金に関するご相談も大歓迎です。専任カウンセラーがあなたの状況をお伺いし、最適なプランを一緒に考えます。「まだ具体的に決めてないけど話だけ聞きたい」でもOK!
全国(東京・大阪他)およびオンラインでカウンセリング実施中です。料金は一切かかりませんので、お気軽にご利用ください。
私たち成功する留学は、大学生の皆さんが金銭的な不安なく留学に踏み出せるよう、全力でサポートいたします。「費用を理由に夢を諦めてほしくない」------その想いでスタッフ一同取り組んでおります。ぜひ一度、無料相談にお越しください。あなたの「成功する留学」を応援します!
(※本記事の情報は2025年現在のものです。制度内容は変更になる場合がありますので最新情報の確認をお願いいたします。)
この記事を監修した人

岡野 健三
「成功する留学」代表取締役社長 / 一般社団法人海外留学協議会(JAOS) 理事
40年以上・25万人超の支援、アジアNo.1エージェント“殿堂入り”をした「成功する留学」の代表を務める。高校留学・海外大学の進学、編入、ファウンデーション、大学院まで、英語力・学力・費用の制約を超えるプランをご提案。
留学について知ろう!
成功する留学だからできること

カウンセラーは留学経験者なので、気兼ねなくご相談いただけます。
豊富な経験と知識で、一人ひとりに合った留学プランをご提案します。
▼ご質問やご不明点はお気軽にご相談ください!
▼留学デスクで個別相談する日程を予約しよう
全国どこからでもオンラインでご相談いただけます!