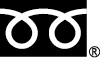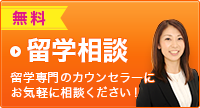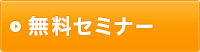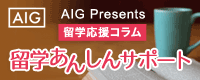海外大学院留学完全ガイド|MBA・大学院進学の費用・条件・英語力を徹底解説

海外大学院への留学は、キャリアの可能性を大きく広げる経験です。
最先端の知識や高度な専門スキルを習得できるため、特にグローバル企業や研究機関では、海外の大学院で得た学位や経験が高く評価される傾向にあります。
異文化環境で生活し学ぶことで、語学力やコミュニケーション能力、柔軟な適応力が身につき、国際的な視野を広げることにもつながります。
経験豊富なカウンセラーに分からないことを聞いてみよう!
この記事を監修した人

岡野 健三
「成功する留学」代表取締役社長 / 一般社団法人海外留学協議会(JAOS) 理事
40年以上・25万人超の支援、アジアNo.1エージェント“殿堂入り”をした「成功する留学」の代表を務める。高校留学・海外大学の進学、編入、ファウンデーション、大学院まで、英語力・学力・費用の制約を超えるプランをご提案。

英語・学力・費用...不安があっても海外大学進学・留学は諦めなくてOK。創業40年・25万人サポートの【成功する留学】が、1年の留学から、4年の正規進学まで最適ルートを無料提案。高校生・大学生・社会人すべてOK。オンライン相談無料。奨学金/出願手続き/英語力アップまでワンストップ。
もっと、沢山の人が"広い世界"を知り、理想の学生生活を実現しますように!!
1. 海外大学院留学とは?基礎知識と魅力
海外の大学院に進学するメリット
海外大学院への留学は、キャリアの可能性を大きく広げる経験です。
最先端の知識や高度な専門スキルを習得できるため、特にグローバル企業や研究機関では、海外の大学院で得た学位や経験が高く評価される傾向にあります。
異文化環境で生活し学ぶことで、語学力やコミュニケーション能力、柔軟な適応力が身につき、国際的な視野を広げることにもつながります。
海外大学院留学の種類|修士・博士・MBAの違い
海外の大学院には、さまざまな種類の学位プログラムがあります。それぞれ目的や内容が異なるため、志望に合ったプログラムを選ぶことが重要です。
それぞれの学位プログラムの特徴は以下のようになります。
- 修士課程(Master's Program):特定分野の専門知識を深める課程で、通常1~2年で修了します。文系・理系問わず幅広い専攻があり、研究論文の提出が要求されるケースが多くあります。
将来のキャリアのために専門性を高めたい人や博士課程進学を目指す人に適しており、文学修士(M.A.)、理学修士(M.S.)など、専攻に応じた学位が授与されます。
教育学(M.Ed)や工学(M.Eng)、法学(LLM)などの専門職学位も修士課程の一種です。制度や学位の分類は国によって異なるため、志望分野の要件を事前に確認しておくことが大切です。 - 博士課程(Ph.D. Program):研究者養成を目的とする最上位の学位課程で、修了までに3~6年程度を要します。独自の研究を行い博士論文を提出する必要があり、将来大学教員や研究職を志す方向けです。
取得難易度は高いですが、世界トップクラスの大学の博士号は研究者キャリアにおいて国内外で有利になるとされています。 - MBA課程(経営学修士):MBAはビジネス・経営に特化した修士課程の一種です。
主に社会人経験を積んだ人を対象としており、金融、経済、マネジメント、リーダーシップなど仕事に直結する総合的な知識を身につけられます。
理論より実務重視で、ケーススタディやグループワークを中心に授業が進められます。他分野の修士課程と比べ授業料が高額である一方、卒業後の年収増加やキャリアアップ効果も大きいとされているのがMBAです。
在学中に培った知識や人脈が起業に役立ったり、帰国後の転職の後押しとなったりする例も多く見られます。
2. 海外大学院留学の費用
海外大学院留学で人気のアメリカ、イギリス、オーストラリアの3カ国について、MBAとその他修士課程の費用目安を紹介します。
MBA・修士課程留学の費用目安(アメリカ・イギリス・オーストラリア)
留学にかかる費用は、大きく「学費」と「生活費(住居費、食費、通信費など)」に分けられます。そのほかに航空券代や保険代、ビザ申請費用、教材費なども必要です。
国や専攻、留学期間によって総費用に変動はありますが、国別・プログラム別の総費用目安は下記の通りです。
| 国 | MBA | コース期間の目安 | 学費(総額) | 生活費(総額) | 総費用(目安) |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | MBA | 2年間 | 約1,000万〜2,500万円 | 約500万~1,200万円 | 約1,700万~4,000万円 |
| その他修士 | 2年間 | 約400万~1,200万円 | 約500万~1,200万円 | 約1,000万~2,600万円 | |
| イギリス | MBA | 1年間 | 約600万〜1,800万円 | 約250万〜600万 | 約1,000万~2,500万円 |
| その他修士 | 1年間 | 約350万~1,000万円 | 約250万〜600万 | 約800万~1,800万円 | |
| オーストラリア | MBA | 1~1.5年間 | 約600万〜1,000万円 | 約200万~500万円 | 約1,000万~1,800万円 |
| その他修士 | 1~2年間 | 約300万~800万円 | 約200万~500万円 | 約800万~1,500万円 |
理系コースは研究施設や実験設備が必要な分、文系より高額になる傾向があります。
また、同じ国でも大学のランキングや立地、国公立・私立の違いによって学費や生活費は変動します。
一般に有名校ほど学費は高額で、例えばロンドンやボストンなど大都市にある学校は生活コストも割高です。逆に地方都市の大学では総費用1,000万円以下に抑えられるケースもあります。
大学公式サイトでは想定生活費が公開されている場合も多いので、志望都市の物価を事前によく調査し、ゆとりを持った資金計画を立てることが重要です。
資金調達方法:奨学金・教育ローン・勤務先からの支援(社費留学)
大学院留学の資金調達には、以下のような方法があります。
- 奨学金:大学が提供する奨学金のほか、日本政府(JASSO、文部科学省)や民間団体などが提供する外部奨学金があります。
外部奨学金には、返済不要の「給付型」と返済義務がある「貸与型」があり、選考では成績や計画書、語学力などが審査されます。
競争率は高いですが、授業料全額や生活費の一部がカバーされるため、挑戦する価値は大きいでしょう。
- 教育ローン:日本政策金融公庫や民間銀行の教育ローンを利用する方法もあります。借入れには金利がかかるものの、必要な資金を一時的に確保できるため、自己資金による負担を軽減する手段として有効です。
- 勤務先からの支援:会社員の方は勤務先で社費留学(企業派遣留学)制度があるかも確認してみましょう。
「卒業後一定期間は復職し勤務すること」などの条件が付く点に注意が必要ですが、社費留学にできれば、自身の負担を最小限に抑え、休職扱いで留学できます。
3. 海外の大学院に行くには何をする?
海外大学院進学までの一般的なステップは以下のようになります。
- 情報収集と大学選び(出願1~2年前)
留学の目的や専攻分野を明確にし、希望国・大学のリストアップを始めます。各大学の世界ランキングや専攻ごとの評価、必要な入学要件(学位や試験)を調べ、自分のプロフィールで現実的に目指せる学校を選定しましょう。
可能なら留学経験者や留学エージェントに相談し、生の情報も集めましょう。 - 語学試験・標準テスト準備(出願1~1.5年前)
TOEFLやIELTSなど英語試験の勉強を始めましょう。MBA志望なら、並行してGMATの勉強も必要です。必要なら複数回の受験を想定した計画を立てましょう。 - 出願書類の準備(出願半年前~)
大学の成績証明書や卒業証明書は英文で取り寄せておきます。履歴書や職務経歴書、志望理由エッセイの作成を進め、推薦状の依頼も早めに進めましょう。 - 出願実施(締切の数ヶ月前まで)
出願はオンラインで行うことがほとんどです。志望校ごとにオンライン出願ポータルへの登録を進め、各大学院の出願締切日に合わせてオンラインで出願書類を提出します。 - 合否通知・入学手続き(入学半年前)
出願後、書類審査を経て合格者にはメールや出願ポータルを通じて合否通知が届きます(MBAでは面接審査後に合否となる学校もあります)。
合格したら、入学意思表示のため指定の期日までにデポジット(入学金)を支払い、正式に入学手続きを進めましょう。併願校から複数合格した場合は進学先を決定し、他校には辞退連絡をします。 - ビザ申請・渡航準備(入学3~4ヶ月前)
進学先が決定したら、学校から発行される入学許可証(アメリカならI-20、イギリスならCASなど)を受け取り、学生ビザの申請を行います。ビザ申請では、パスポートの有効期限にも注意しましょう。
並行して留学先の住居手配、航空券や海外留学保険の手配も進めます。
出発前にオリエンテーションがある場合は積極的に参加し、不安点を解消しておきましょう。
社会人が大学院留学を目指す場合、職場への休職の相談や退職の交渉なども必要になります。時間に余裕を持ち、一つひとつ着実に準備を進めましょう。
4. 分野別大学院留学ガイド|MBA・理系・文系それぞれの特徴と選び方
MBAの種類・特徴・選び方
MBAには大きく分けて、下記の3つのタイプがあります。
- フルタイムMBA:平日昼間に授業があり、1〜2年で修了するプログラム。仕事を離れて学業に集中したい人が主な対象。
- パートタイムMBA:仕事を続けながら、数年かけて履修するプログラム。夜間や週末に現地またはオンラインで授業が行われます。
- エグゼクティブMBA:管理職クラスの経験豊富な人や経営幹部向けのプログラム。授業は月1回の集中講義や週末のみの講義で構成され、仕事を続けながら学べるのが特徴です。
日本から海外のMBAを目指す場合は、学生ビザの取得要件も満たせる「フルタイムMBA」が基本の選択肢となります。
フルタイムMBAの学生は、3~5年程度の職務経験を持つ20代後半から30代前半の社会人が中心ですが、年齢制限はなく、30代・40代以降でも挑戦でき、むしろ社会人経験が長いほど学びを実践に結びつけやすい点が魅力です。
MBAと一口にいっても、ファイナンスに強いプログラムや起業家育成に定評のあるプログラムなど、専攻やカリキュラムの特色は学校によって大きく異なります。
下記は各大学のMBAプログラムの特徴の例です。
| 大学 | 特徴 | プログラムの長さ |
|---|---|---|
| ハーバード大学(アメリカ) | ジェネラルマネジメント教育に定評 | 約2年 |
| スタンフォード大学(アメリカ) | ジェネラルマネジメント教育に定評 | 約2年 |
| シカゴ大学(アメリカ) | 分析・金融に強い | 約2年 |
| ロンドン・ビジネス・スクール(LBS)(イギリス) | 金融ネットワークが強い | 約2年 |
| メルボルン大学(オーストラリア) | ジェネラルマネジメント教育に定評 | 約1年 |
たとえば、グローバル企業への転職を目指すなら国際的評価の高い有名校を、起業志向があるならネットワークや支援制度が整った学校を選ぶとよいでしょう。
単にランキングだけを見るのではなく、各プログラムの内容や特徴を比較し、自分のキャリア目標にどれだけ合致しているかを検討することが重要です。
理系コースの特徴・選び方
理工系・自然科学系の修士や博士課程では、入学後に特定の研究プロジェクトに所属し研究を進めるのが一般的です。そのため出願前から自分の興味分野とマッチする研究を行っている大学・教授を探し、アプローチすることが成功の鍵になります。
事前に論文や大学HPで教授の研究内容を調べ、志望理由書で明確な動機を示すと好印象です。
また、理系は奨学金やRA/TAとしてリサーチ費用・給与を得られる機会もあります。特に米国PhDでは多くの大学がフルファンド(授業料免除+生活費支給)を用意しています。修士レベルでも、大学や教授のプロジェクト予算から学費免除・スカラーシップを得られるケースがあります。
分野別の有名大学
| 分野 | 有名大学 |
|---|---|
| 工学 |
|
| コンピュータサイエンス |
|
| バイオ・生命科学 |
|
研究設備や環境も留学先選びの大切な観点です。世界トップレベルの大学には最先端の実験装置や豊富な研究資金があり、これは日本国内では得がたいメリットです。また多国籍の研究者仲間と切磋琢磨できる刺激的な環境も海外ならではです。
帰国後のキャリアも見据え、自分の専門分野では海外学位がどう評価されるかも情報収集して、大学・コースを選びましょう。
文系・社会科系コースの特徴・選び方
文系・社会科学系(経済学、政治学、社会学、国際関係、教育学等)のコースでは、講義やセミナーでのディスカッションやエッセイ執筆が重視されます。少人数制のセミナーで学生同士や教員と議論を深めるスタイルが主流で、日本の大学のような一方通行の講義より双方向の討論形式が多い点が特徴です。
読まなければならない文献量も多く、毎週数百ページのリーディングが課されることも珍しくありません。したがって高いアカデミック英語力(特にリーディング&ライティングの力)が要求されます。
評価方法も筆記試験よりエッセイやリサーチペーパー提出が中心です。
最終的に修士論文の提出が必要なプログラムも多く、指導教員の下で自主研究を行い論文を完成させます。
コースによっては、プロジェクト型の科目が組み込まれ、教育現場での実習や、クライアントの課題を分析するケースプロジェクトに取り組む場合もあります。
分野別の有名大学
| 分野 | 有名大学 |
|---|---|
| 国際関係学 |
|
| 教育学 |
|
| 社会学・人類学 |
|
卒業後に国際機関やNGOで働きたいなら関連インターンが充実した学校、博士課程に進み研究者になりたいなら研究手法の訓練がしっかりした学校を選ぶなど、ゴールから逆算したプランニングが大切です。
5. 国別情報|アメリカ・イギリス・オーストラリア
アメリカの大学院の特徴
アメリカは世界で最も多くの留学生を受け入れている国です。
一般的に修士課程は2年制(MBAも通常2年)、博士課程は5年前後で、出願時にはTOEFLやIELTSに加え、多くの専攻でGRE(大学院共通試験)のスコア提出が求められます(※MBAではGMATが主流)。
通常F-1ビザ(フルタイムの学生ビザ)が発行され、卒業後はOPT(Optional Practical Training)という制度を利用して最長12か月間、そのままアメリカに滞在し、専攻分野に関わる業種の就労研修を受けることも可能です。
出願スケジュールと締切
一部のプログラムでは春入学(1~3月開始)もありますが、秋入学(8~9月)が主で、多くの大学が12月〜翌年1月ごろに出願締め切りを設定しています。
MBAコースの場合は、秋から冬にかけて複数回の締切を設けるラウンド制を採用しているところもあります。
アメリカの代表的な大学
アメリカは世界ランキング上位100校に多くの大学がランクインしており、トップ大学が集まる国の1つです。
以下はアメリカの代表的な大学です。
- ハーバード大学(QSランキング5位)
- スタンフォード大学(QS3位)
- マサチューセッツ工科大学(MIT)(QS1位)
- カリフォルニア大学バークレー校(UCB)(QS17位)
- シカゴ大学(QS13位)
- カリフォルニア工科大学(QS10位)
※QSランキングは2025年の結果を反映
理工系ではMITやカーネギーメロン大学、カリフォルニア工科大学、ミシガン大学などが有名で、文系ではハーバード大学やコロンビア大学がよく知られています。
アメリカは大学院の種類が豊富で、アイビーリーグから州立大学まで選択肢が多いのが特徴です。
イギリスの大学院の特徴
イギリスもアメリカに次いで留学生数が多い国です。
大学院教育の歴史が長く、特に社会科学・人文科学分野で世界的な名門校が揃っています。修士課程は1年制が主流で、多くのコースは9月に始まり翌夏に修了します。
イギリスでは、MBAの場合はGMATを要求する学校もありますが、基本的には大学の成績と英語力証明書、推薦状やエッセイが主な出願書類です。
イギリスへ留学するには、Student Visa(学生ビザ)の取得が必要です。卒業後の進路としては、Graduate Route制度を利用することで、修士号取得者は最長2年間、博士号取得者は最長3年間、イギリスに滞在して就労することもできます。
出願スケジュールと締切
イギリスの大学院への出願は、コース開始の約1年前から始まり、定員に達するまで出願を受け付ける「ローリングアドミッション方式」が一般的です。人気コースは早期に締め切られることもあるため、早めの出願が安心です。
トップ校では締切日が明確に設定され、ビジネス系では複数回の締切を設ける「ラウンド制」を採用する場合もあるため、志望コースに関する出願情報は早めにチェックを進めましょう。大学の奨学金へ応募ができるのは合格者のみとなるため、スケジュールを事前に確認し、早めに出願手続きを進めるのも大切です。
イギリスの代表的な大学
イギリスには、長い歴史と高い教育水準を誇る大学が数多くあります。以下はイギリスの代表的な大学です。
- オックスフォード大学(QSランキング4位 / 2017年以来9年連続THEランキング1位)
- ケンブリッジ大学(QS6位)
- インペリアル・カレッジ・ロンドン(QS2位)
- ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(QS9位)
- ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)(QS56位)
- キングズ・カレッジ・ロンドン(KCL)(QS31位)
- エディンバラ大学(QS34位)
- マンチェスター大学(QS35位)
- ブリストル大学(QS51位)
※QSランキングは2025年の結果を反映
なかでも、LSEは社会科学、ICLは工学・医学、キングス・カレッジ・ロンドンは人文科学、エディンバラ大学は情報学といった強みがあります。
イギリスの大学院ではほとんどの場合、コースを1年で修了できるため、日本人社会人にも選ばれやすい選択肢となっています。
オーストラリアの大学院の特徴
オーストラリアも英語圏の留学先として人気を集める国です。
主要8大学(Group of 8)は研究水準が高く、オーストラリア全体で見てもトップ100に複数校がランクインしています。
修士課程は1~2年制とコースにより異なりますが、研究志向のMaster of Philosophy(MPhil)は2年程度、授業主体のMaster's(Coursework)は1~1.5年が一般的な目安です。
オーストラリアへ留学するには、学生ビザ(Subclass 500)を取得します。修了後には卒業生ビザを申請でき、修士号取得者は2年間、博士号取得者は3年間の滞在・就労が認められます
出願スケジュールと締切
出願時期は2月入学の場合、前年の9~11月頃、7月入学の場合その年の3~4月頃が締切の目安です。南半球のため2月が学年開始である点に注意が必要です。
オーストラリアの代表的な大学
オーストラリアは人口あたり留学生比率が高く、大学によっては学生の30%以上が留学生という環境もあります。以下はオーストラリアの代表的な大学です。
- メルボルン大学(QSランキング19位)
- ニューサウスウェールズ大学(UNSW Sydney)(QS20位)
- シドニー大学(QS25位)
- オーストラリア国立大学(ANU)(QS32位)
- モナシュ大学(QS36位)
- クイーンズランド大学(QS42位)
※QSランキングは2025年の結果を反映
分野別では、モナシュ大学は薬学・薬理学で世界トップクラス、ANUは政治学や国際関係で知られるなど、それぞれ強みを持っています。
オーストラリアの大学はイギリス式の教育システムを踏襲しているため、学位の国際認知度も高く、各国からの留学生受け入れ実績が豊富です。
また、留学生比率が高く、多文化環境で学べる点もメリットです。
英米に比べ費用が抑えられるケースも多く、費用対効果の高い留学先として人気が高まっています。
6. 海外大学院進学の条件と準備
志望するコースが決まったら、大学公式サイトを確認し、各コースページで要件や必要書類を確認しましょう。
下記で主な要件や書類についても解説します。
学歴・GPAと必要書類
海外の大学院に出願するためには、基本的に学士号(4年制大学卒業資格)が必要です。加えて、大学の成績(GPA)も重要な選考基準となります。
出願に必要な書類と要件目安は下記のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学歴要件 | 学士号を取得(大学卒業)していること |
| GPA |
|
| 主な出願書類 |
|
| 英語力要件の目安 |
|
アメリカの大学院やMBAコースでは、GREやGMATのスコア提出が求められる場合もあります。
志望専攻によってはエッセイ課題や研究計画書、ポートフォリオ(作品集:建築や美術系の場合)の提出が求められ、面接試験が課されることもあります。
必要書類は大学や専攻ごとに異なるため、志望コースの入学要項をしっかりチェックすることが大切です。
英語要件については、総合得点だけでなく各セクションの最低点を定めている場合も多くあります。
イギリスやオーストラリアの大学院では、英語要件を満たせなくても条件付合格(Conditional Offer)が出され、入学前に指定の語学コースを受講することで英語要件を満たせる場合があります。
一方、アメリカではそうした条件付き合格制度がないことがほとんどです。出願時までに必要スコアを取得しておかなくてはなりません。
トップ校であるほど英語要件も高くなる傾向があるため、早くから対策を進めておきましょう。
必要書類と準備ポイント
各書類作成のポイントについては、以下も確認してください。
| 書類 | 準備ポイント |
|---|---|
| 大学の卒業証明書、成績証明書(英文) | 発行に時間がかかることもあるため、早めに発行依頼をしましょう。英文の正式書式でもらい、不備がないか確認します。 |
| 志望理由書 | 志望大学ごとにカスタマイズして作成するのが理想です。各プログラムで学びたい内容、その大学でなければならない理由、自分の目指すキャリアとの関連を盛り込み、説得力あるストーリーを作ります。字数制限内で簡潔かつ具体的に書き、読み手に熱意が伝わるよう心がけましょう。 |
| エッセイ | 志望コースによってはエッセイ課題が課される場合もあります。 MBAではエッセイ課題があることが多く、リーダーシップ経験や挫折からの学びなどよく問われるテーマについて、自身の体験をエピソード形式でまとめておくと書きやすくなります。 |
| 推薦状 | 信頼できる推薦者に依頼し、締切より十分前にドラフトをお願いすることが大切です。最近はオンラインで直接推薦者がアップロードする方式が多く、依頼者が内容を確認できない場合もあるため、日頃から自分の業績や志望について推薦者とコミュニケーションを取っておくと良いでしょう。 |
| 英文履歴書(CV) | フォーマットが日本と異なり、氏名・連絡先から始まり学歴・職歴・スキル・業績と箇条書きで1~2ページ程度にまとめるのが一般的です。 読み手が一目であなたの経歴を把握できるよう工夫しましょう。 |
| 英語力証明書(TOEFL/IELTS) | 試験から2年以内のスコア提示が必要となるため、試験の有効期限にも注意しましょう。 |
| 研究計画書 | 志望専攻や大学によっては、研究計画書の提出が課されることがあります。特に博士課程や研究色の強い修士課程では、応募段階で具体的な研究計画の概要を問われたり、指導教員となる教授とのインタビューが実施されるケースがあります。 書くべき内容は大きく分けて、(1)研究背景と問題設定、(2)研究目的・問い、(3)研究方法、(4)予想される成果や意義、(5)参考文献です。ポイントは、その大学の教授が指導可能なテーマであることを示すことです。 事前に志望先の教授の研究分野を調査し、それに沿ったテーマ設定をしましょう。 |
書類審査とは別に、面接が審査に含まれる場合もあります。
対面またはオンラインで面接が行われ、教授や卒業生が面接官となる場合もあります。
問われる内容は志望コースによってもさまざまですが、志望動機、キャリアプラン、過去の経験、自分の強み・弱みなどは英語でスムーズに伝えられるよう準備をしておきましょう。
自分のエッセイ内容と矛盾がないよう一貫したストーリーで答えることが大事です。
服装や所作もビデオでチェックし、オンラインならカメラ写りや音声環境も事前に確認し、笑顔とアイコンタクトを忘れず、自信を持って臨んでください。
実践的な英語力向上法(社会人向け)
海外大学院留学のためには、英語力も重要なポイントです。
社会人が仕事の合間に英語力を伸ばすには、日常に英語学習を組み込む工夫が大切です。以下に実践的な取り組み方法をいくつか紹介します。
- 通勤・スキマ時間の活用
通勤時間や昼休みなどのスキマ時間を英語学習に充てましょう。
通勤中に英語ニュースのポッドキャストやオーディオブックを聞いてリスニング力を鍛えたり、単語アプリでボキャブラリー強化をしたりするのも有効です。 - オンライン英会話・コーチング
毎日25分でもオンライン英会話でネイティブと会話練習すれば、スピーキング力と瞬発的な英語思考力が養われます。仕事で英語を使う機会がない人ほど、アウトプットの場としてオンラインレッスンは有益です。
予算に余裕があれば英語コーチングスクールに通い、専属トレーナーの下で短期間でスコアアップを図るのも一つの手です。 - 英語で情報収集・発信
普段から興味のある分野の情報を意識的に英語で収集しましょう。
たとえばIT業界で働いているならTechCrunchやWIREDを英語で読んだり、経済ならThe Economistの記事を英語で読んだりするのも効果的です。
また、英語で日記やブログを書くのもおすすめです。自分の考えを英文で表現する練習になり、語彙や文章構成力が磨かれます。英作文したものは文法チェックツールやネイティブに見てもらい、改善を重ねましょう。 - ミニ留学・英語合宿:まとまった休みが取れる場合、1~2週間でも短期留学や国内英語合宿に参加するのも方法です。
集中的に英語に浸かることで「話せない恥ずかしさ」の殻を破り、自信をつける効果があります。 - 業務で英語を使う機会を作る
もし可能なら、職場で海外プロジェクトへの参加を志願したり、英語資料の作成を引き受けたりして、実践的に英語を使う機会を作りましょう。実践の中で使う英語は身につきやすく、モチベーション維持にもつながります。周囲に外国人の同僚がいるなら、積極的に会話するのも有効です。
社会人は限られた時間の中で成果を出す必要があります。
何より大事なのは「毎日欠かさず英語に触れる」習慣です。忙しい日でも、5分で良いので英語を読む・聞く・話す・書くいずれかの行動をしましょう。それが半年〜1年前から積み上がれば、大きな力となって留学に備えられるはずです。
7. 海外大学院留学後のキャリアと費用対効果
海外大学院留学で得た学位や経験への評価では、分野によるところはありますが、おおむね以下のような傾向があります。
- 日本国内の企業:日本国内企業は、以前に比べ海外学位取得者の採用に前向きになってきています。特に英語力や国際感覚、専門知識が評価され、コンサルティング、金融、商社、ITなどグローバル展開する業界では採用につながるケースが増えています。
一方で新卒一括採用という日本特有の慣行も根強く、中途採用では「経験年数に見合う即戦力」を期待される傾向があります。海外大学院卒業後の就職活動では、スキルや専門性を自らアピールする工夫も必要です。 - 海外・外資系企業:海外や外資系企業へのアピールでは、海外学位が役立つ場面も多いでしょう。MBAであれば欧米のコンサルや金融機関、テック企業などがリクルーティングフェアを開催し、在学中から内定を出すようなケースもあります。
- 起業・フリーランス:MBA留学は特に起業家輩出が多いことで知られ、クラスメイト同士でスタートアップを立ち上げる例も多くあります。
アート・デザイン系の留学では現地でフリーランスのクリエイターとして活躍する道を切り開く人もいます。帰国後フリーランスで通訳やコンサルタントとして独立するケースもあり、本人の実力次第ではありますが、キャリアの一つの形です。
海外大学院卒という肩書だけで劇的に待遇が良くなる保証はないものの、専門性+語学力+国際経験を兼ね備えた人材として、大きなアドバンテージを得られる可能性は高くなるといえます。帰国後、留学で得た経験やスキルをどう活かすかも重要な点です。
大学院留学の費用対効果の観点では、MBAのようなビジネス系学位は、帰国後に収入が増える傾向があり、数年で留学費用を回収できるケースも少なくありません。公共政策や国際関係の修士号を取得した人の中には、国際連合や世界銀行といった国際機関に就職する人もいます。
それ以外の分野でも、帰国後に優れたキャリアを築いている人はたくさんいます。
留学の費用対効果を高めるためには、積極的に現地のキャリアイベントに参加し就職先を探したり、教授や同級生と人脈を築き将来のビジネスに繋げたりするなど主体的に動く努力が大切です。
8. 注意点とFAQ
大学院留学に年齢制限はありますか?
大学院留学に年齢上限はほとんどありません。MBAでは平均年齢が約28歳とされつつも、40〜50代でも入学する人はおり、社会人経験はむしろ評価されます。博士課程でも30代での入学は珍しくありません。
ただし、日本の中途採用市場では年齢制限があることもあり、帰国後に日系企業に就職する場合は注意が必要な場合があります。
社会人が留学する場合、キャリアを一時中断することになるため、留学中の空白期間をどう過ごし、何を得たかが重要になります。帰国後、留学で得たスキルや経験をしっかり説明できるよう自己研鑽に励みましょう。
大学院留学中にアルバイトはできますか?
学生ビザで滞在する場合、多くの国で留学生のアルバイトが一定時間まで認められています。
オーストラリアやイギリスでは週20時間までの就労が可能です。
アメリカは原則としてキャンパス内でのアルバイトに限られますが、週20時間以内の就労が認められます。
ただし、あくまで留学の本分は学業であり、アルバイトは補助的なものです。現地での収入を前提に資金計画を立てるのではなく、日本出発前に十分な留学費用を確保しておくことが重要です。
9. よくある失敗と対策
最後に、海外大学院留学でよくある失敗例と、その対策方法をお伝えします。
- 出願準備の遅れ:語学スコアや推薦状の準備が間に合わないケース
→ 対策:海外大学院留学のためには、早めの行動と余裕を持ったスケジュール管理が大切です。 - 英語力不足による学業・生活の困難:準備が足りず授業に付いていけない、孤立してしまうなどのケース
→ 対策:アカデミック英語や専門用語の事前学習と、現地でも積極的に学ぼうとする姿勢を持つことが大切です。間違いを恐れず、挑戦しようとする気持ちも大切です。 - 資金計画の甘さ:費用の見込みが甘かったり、為替変動で想定以上に費用がかかり、資金が足りず、生活困窮や留学中断になってしまうケース
→ 対策:予算は多めに見積もり、支出管理を徹底しましょう。奨学金やローンもできる限り活用しましょう。想定外の出費があることもあるため、資金は総額に20%ほど上乗せした額を用意しておけると安心です。 - 目的不明確なままの留学:明確な目標設定がないままに留学してしまい、帰国後のキャリアに迷ってしまうケース
→ 対策:留学の目的や卒業後の進路を事前に明確にし、それに沿った専攻や科目の選択をしましょう。ゴールを明確にすることで、モチベーションアップにもつながります。 - メンタル不調や燃え尽き症候群:慣れない環境と勉強漬けの日々でストレスが溜まり、心身のバランスを崩してしまうケース
→ 対策:頑張る気持ちも大切ですが、時には休憩や気分転換の時間をとることも大切です。同じ境遇の留学生仲間と愚痴を言い合うことも助けになります。大学のカウンセリングサービスやメンター制度も積極的に利用し、セルフケアを怠らず、心の健康にも目を向けるようにしましょう。
誰しも多少の失敗は経験しますが、そこから学んでリカバーできれば大丈夫です。周囲のサポートも借りつつ、自分の留学生活を実りあるものにしてください。
失敗を恐れず挑戦した先に、大きな成長と成功が待っていることでしょう。
海外大学進学の費用について相談してみよう!
海外に進学をしよう!
留学について知ろう!
成功する留学だからできること

カウンセラーは留学経験者なので、気兼ねなくご相談いただけます。
豊富な経験と知識で、一人ひとりに合った留学プランをご提案します。
▼ご質問やご不明点はお気軽にご相談ください!
▼留学デスクで個別相談する日程を予約しよう
全国どこからでもオンラインでご相談いただけます!